
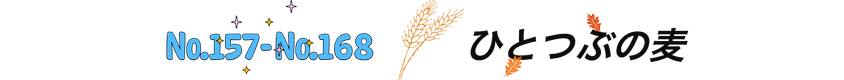
-------------------------------------
(NO.168)
none
-------------------------------------
(NO.167)
none
-------------------------------------
(NO.166) 平和と忍耐の人イサク
「主はその夜、彼(イサク)に現れて仰せられた。
『わたしはあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。わたしがあなたとともにいる。わたしはあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。わたしのしもべアブラハムのゆえに。』 イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらは、そこに井戸を掘った。」 (創世記26章24~25節)
アブラハム、サラ夫婦の間には、子供がありませんでした。妻にとって、子供がないということは、恥との思いがありましたので、妻サラは大変悩みました。しかし、神は夫アブラハムを外に連れ出し、天を見上げさせ「星を数えることができるなら、数えてみなさい。あなたの子孫はこのようになる。」(創世記15章5節)と約束していました。(その子イサクにも同じような約束をしました。)
アブラハムは神の約束を信じていました。時が来て、神の約束通り、サラは男の子を産んだのです。その子はイサクと呼ばれました。
今日、多くのキリスト者がイサクの名前をクリスチャンネームとするほどに、愛され、親しまれているのです。彼はあまり自己主張しない、どちらかと言うと内気で、愛情こまやかなタイプです。
イサクはパレスチナに住んでいました。その地においては、水は特に貴重なものでした。苦労して井戸を掘り水の湧き出るのを喜んでいると、その地の羊飼いたちは「この水はわれのものだ」と主張しますと、イサクは争いを避けて他に移動しました。そういうことは何回も繰り返されました。全てを知り給う神は、そのようなイサクを祝福し、井戸を掘るたびに水を湧き上がらせ、家畜やしもベたちを豊かに増し加えてくださったのです。
「悪に負けてはいけません。かえって、善をもって悪に打ち勝ちなさい。」
(ローマ人への手紙12章21節)
-------------------------------------
(NO.165) 人とは、何者なのでしょう
「あなたの指のわざである天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは、
何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人の子とは、何者なのでしょう。
あなたがこれを顧みられるとは。…」 (詩篇8篇3~4節)
ここに記述しました前後にもことばがありますが、本篇はイスラエルの王でもありました
ダビデの作です。ダビデはなかなかの詩人です。この詩篇八篇において作者は、天地万物の創造主なる神の栄光と尊厳性をあらわすとともに、脆弱(ぜいじゃく)で小さな存在である人をも顧みられるご恩寵ゆたかな神を讃美しているのです。晴れ渡った夜、空を見上げるとき月や点点と光る星が目にとびこんできます。そのとき私はこのみことばや、
「天は神の栄光を語り告げ、大空は御手のわざを告げ知らせる。」(詩篇19篇1節)
を想い起こします。そして神のすばらしさをほめたたえます。
しかし、いったん目を地上に向けますとき、「人とは」(エノシュ~ヘブル語)、全能の神に
対して、たよりなさ、無力、死ぬべき存在。「人の子」(ベン・アダム)(土から生まれた子)
(もろくて弱い)存在の意。
今も神はこのような人間を顧みておられるのです。「顧みる」とは「恵み深くさがし求めら
れる」という意味です。恵み深く人をさがし求めておられる神は、具体的にご自身の御子イエス・キリストを人間の世界に遣わし、キリストを十字架上で犠牲にすることによって罪を贖われたのです。
「…あなたがたが、…むなしい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちる物にはよらず、傷もなく汚れもない小羊のようなキリストの、尊い血によったのです。」
(ペテロの手紙第一 1章18~19節)
キリストは、私たちすべての人の唯一の救い主です。
-------------------------------------
2012年8月 (NO.164) 教会の土台はイエス・キリスト
「というのは、だれも、すでに据えられている土台のほかに、ほかの物を据えることは
できないからです。その土台とはイエス・キリストです。」
(コリント人への手紙第一 3章11節)
当時のコリントの町は、道徳的に非常に乱れた町でした。その町にキリストのしもべ、パウロは苦労しながらイエス・キリストの福音(良い知らせ)を宣べ伝えたのです。福音という種が芽を出し、花が咲き、実を結んだのです。即ち、キリストを信じるクリスチャンが生まれたのです。1人では教会とは言いませんが、クリスチャンのグループを教会と呼びます。その教会がコリントの町に誕生したのです。
キリスト教会にとって最も大切なことは、外観が立派だとか、美しく高価な材料を沢山用いているというようなものではありません。なかなか目に付きにくい土台そのものが最も重要なのです。教会の土台とは、教会が立っている信仰告白(教理)のことです。換言すれば、聖書を神のことばと信じる聖書信仰です。キリスト教の歴史は2000年以上の古さがありますので、その間、様々な教えを主張する人たちが現れました。それは今日も変わりません。これは大事なことです。教会に通っていながら真の救いにあずかれなかったとするなら、これ以上に不幸なことはありません。
「イエスは言われた。『わたしは、よみがえりです。いのちです。わたしを信じる者は、
死んでも生きるのです。』」 (ヨハネの福音書11章25節)
私たちの身代わりに十字架にかかり、罪の贖いをなし、三日目に死よりよみがえられ、今も生きておられ、信じて寄り頼む者を確実に救い、永遠のいのちを与えたもうイエス・キリストが高尾キリスト教会の土台であり、あなたや私の唯一の救い主なのです。このような素晴らしい救い主を与えられていることに感謝し、共に礼拝において神を讃美しませんか。お待ちしております。
-------------------------------------
(NO.163) キリストの十字架は必要だった
「モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子もまた上げられなければなりません。
それは、信じる者がみな、人の子にあって永遠のいのちを持つためです。」
(ヨハネの福音書3章14、15節)
モーセは今から三千数百年前の人です。奴隷として苦境にあえいでいたイスラエルの民を開放し、荒野での生活を経て約束の地へ導くという働きをした有名な指導者です。確かに長期間の荒野での生活は苦しみの連続でした。しかしその期間、神は彼らを忘れていたわけではありません。必要な食べ物や飲む水をもって彼らを養ったのです。だが民は満足しませんでした。つぶやき、不平をならべ、神とモーセに逆らったのです。そのとき神は、民の中に蛇を送り、多くの人々が死にました。このことにより民たちは自分たちの罪を自覚し、モーセに蛇を自分たちの中から取り去ってくれるよう祈ってほしいと願ったのです。モーセは民のために祈りました。そして神の指示を受け、一つの青銅の蛇を作り、旗ざおの上にかかげました。蛇にかまれた者でも、その青銅の蛇を仰ぎ見た者は死ぬこともなく、生き延びたのです。(民数記21章4節以下)
「モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子もまた上げられなければなりません。」
「人の子」とは特別のことばで、キリストのことです。神に背を向け、罪の中にある人々を救うためには、清く、罪のないキリストのみが、罪人の身代わりとなりうるお方でした。
そのためにキリストは自ら進んで十字架におつきになられたのです。
旧約聖書の「青銅の蛇」はキリストを象徴していると言えます。今日、イエス・キリストを私の救い主と信じ、仰ぎ見る人はだれでも救われるのです。
十字架は他の教えにはありません。
キリストを信じ、従う者は、最後の勝利者とされるのです。移り行くものに心を奪われず、
永遠に続くものに、大事な心を向けようではありませんか。
-------------------------------------
2012年6月 (NO.162) 私が弱いときにこそ、私は強い
「…私は、キリストのために、弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱いときにこそ、私は強いからです。」
(コリント人への手紙第二 12章10節)
この手紙は使徒パウロが書いたものです。彼はキリスト者を憎み、無き者にしようとした強烈な迫害者でした。それはキリストをも、キリスト者をもよく知らなかったからです。しかし、よみがえられたキリストに出会ってからは、キリストとキリスト者に対する態度が、180度転換させられたのです。
相手に対する認識不足のために、人を誤解することが、私たちにしばしばあります。人に対してだけでなく、宗教に対しても、そのようなことがよく見られます。
キリスト教に対し正しく認識した彼は、今まで反対して来たキリスト教の伝道者として余生を捧げたのです。伝道者の道は、何時の時代でもきびしいものですが、特にキリスト教会が発足したばかりの紀元一世紀においては開拓期ですから筆舌に尽くし難い困難が伴ったのです。パウロの活動状況は、使徒の働きと言う書に詳しく記されています。
冒頭のみことばは、彼が実際に体験したことです。「私が弱いときにこそ、私は強いからです。」という表現は、事実と反対なことを言っているようで、よく考えると実際のことを言い表しています。いわば逆説的表現といえましょう。
イエス・キリストは確かに十字架上で死なれました。しかし、前からおっしゃっておられた通り復活され、今も生きておられるのです。キリストに仕えるパウロとともにおられ、彼を助けられたのです。私たちは弱い、しかしキリストは強いのです。宣教活動において彼は孤独、苦悩、迫害の連続でした。そのような中で、彼は生けるキリストの力と慰めと助けを受けたのです。今もキリストは彼を信じる者と共にいてくださるのです。そこにキリストにある幸いがあります。
-------------------------------------
(NO.161)
none
-------------------------------------
(NO.160) 死者の中からよみがえられたキリスト
「しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。」
(コリント人への手紙第一 15章20節)
今年の4月8日は、イエス・キリストが死者の中から復活されたことを記念するイースター(復活節)です。キリスト教においてイースターはキリスト教最大の祝祭日です。クリスマスは世界のどなたでもご存知です。しかし、イースターについてはそれほど知られておりません。イースターはクリスマスに優るとも劣らない最高の祝日といえます。
賛美歌153「わが魂よ聞け この知らせを 主(イエス・キリスト)は今死より よみがえりて 勝利の旗 高く掲げ われを天に 招き給う」と救い主イエス・キリストのみわざが歌われています。
十字架上で人々の身代わりの死をとげられたイエス・キリストが、かねてより語っておられた通り、事実、よみがえることによって、人々の罪をあがなうというみわざの完成を鮮明にするとともに、いまだかつてだれもなしえなかった死を征服したことによって、ご自分は神から遣わされた唯一の救い主であることを実証された重要な出来事だからです。
イエス・キリストは神から遣わされ人となられた神であります。神であられ、同時に人間であられるイエス・キリストだけが神と人間とを結び合わせる唯一の仲介者です。神との正常な関係を持たなければならないのにかかわらず人は、神を無視し、神とは無関係に好き勝手な道を歩んでいることは正しい姿ではありません。キリストは人としてこの地上に来られ、神に立ち返るように教えられ、さらにご自分が人間の罪の身代わりに死なれたのです。
神であり、人であられ、死に対して勝利者となられたイエス・キリストこそが私たちの唯一の救い主なのです。
教会においてご一緒に聖書を学びませんか。おいでを心からお待ちしております。
-------------------------------------
2012年3月 (NO.159) いのちのことば
「『 行って宮の中に立ち、人々にこのいのちのことばを、ことごとく語りなさい 』と言った」
(使徒の働き5章20節)
聖書は神のことば、又はいのちのことばと呼ばれています。それは人々を永遠のいのちへ導く作用をなすからです。イエス・キリストの弟子たちはこのみことばを伝えることに命をかけて励んだのです。今も生きておられるキリストの力をいただきながら、病める者たちをいやし、ある者たちを救いに導くという働きをしたのです。弟子たちのめざましい働きに嫉妬と危機感を抱いた指導者たちは宣教中止の命令を出し、さらに身柄を拘束し留置場に入れ、彼らを苦しめたのです。留置場に入れられた時の様子を聖書は次のように記しています。
「ところが、夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、『行って宮の中に立ち、人々にこのいのちのことばを、ことごとく語りなさい』と言った。」
(使徒の働き5章19、20節)
弟子たちはどんなに反対され、妨害されても、いのちのことばを語り告げることを止めませんでした。なぜでしょうか、だれもが主イエスの救いにあずかり、永遠の命を得るためにはいのちのことばを欠かすことができません。どうしても聞かなければなりません。だれかが宣べ伝えなければ救いのことも、永遠の命を得る幸せを知ることもできません。知らないものをだれも求めません。主イエスの弟子たちは、自分の幸せだけで満足せず、1人でも多くの人々が自分たちと同じ救いにあずかって欲しいとの願いをもって、反対されようと妨害されても宣べ伝えたのです。
主イエスは自らを犠牲にしてまでも他者のために生涯を捧げたお方でした。その愛の精神を弟子たちは学んでいました。主イエスほどの深い愛ではありませんでしたが、その愛をもっていのちのことばを語り続けたのです。この主イエスの愛の行為が世界で行われるとしたら、世界はもっと明るくなるのではないでしょうか。
-------------------------------------
(NO.158) 救いに至る門
「わたしは門です。だれでも、わたしを通って入るなら、救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。」 (ヨハネの福音書10章9節)
イエス・キリストはいろいろな「たとえ」を用いてご自分のことや救いについてお話しされました。
ここではご自分を門にたとえておられます。
パレスチナでは羊を飼う人が大勢いました。パレスチナの土地は荒地が多く、農耕地などは限られていました。広い草原に羊を放つということはありません。羊飼いは草のある場所から場所へと移動しながら遠くまで行くのです。ですから羊飼いの経験がものを言うのです。夜は、住まいの隣にある囲いに羊を入れて休ませるわけです。その囲いに入る門(立派な物ではないが)があります。この門が重要です。門を通らないで入る者は羊に害を加える者たちですから厳重に警戒したのです。主イエスは、人々がよく知っている羊の門にご自分をたとえて、人々に真の救いと平安を与える唯一のお方であることを示されました。他の所で主イエスはおっしゃいました。「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、だれひとり父(父なる神様)のみもとに来ることはありません。」(ヨハネの福音書14章6節)ここでも主イエスは、ご自分が道であり、真理であり、いのち(永遠のいのち)です、と唯一性を主張されました。確かにこのように主張し得るお方はイエス・キリストご自身のみです。主イエスは「わたしを通って入るなら、救われます。」と述べ、その後で「安らかに出入りし、」とありますが、聖書では、なんの不安もない平穏な生活を表しています。次の「牧草を見つけます。」は、主イエスにある喜びと平安といのちに生かされるのです。
古くて、新しい教えの数々の聖書からご一緒に学びませんか。ご来会をお待ちしています。
-------------------------------------
(NO.157) 神の平安があなたの上に
「何も思い煩わないで、あらゆるばあいに、感謝をもってささげる祈りと願いによって、
あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに
まさる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれます。」
( ピリピ人への手紙4章6~7節)
昨年の大震災はご当地の方々ならびに、日本の全国民に深い傷と大きな悲しみをもたらしました。特に、被災された方々は、今もなお苦しみと辛い日々を送っていらっしゃいます。その方々のために何もできず祈るだけの自分が情けなく、また不甲斐なく思わされています。ただただ今も1日も早い復興と被災者の方々の暮らしの回復とを切に祈っております。
聖書のおことばが、少しでも多くの人々の慰めとなり力となることを願いつつ目を向けたいと思います。
私たちの人生は、願い通りに平穏無事の日々とは行きません。様々な問題や不測の事態に直面します。また何をどうすれば良いのかも分からないような事柄にも会います。そのような場合、神を知り、信じている者はどのように対応すべきかを冒頭のことばは教えています。
心配事でいっぱいの時、「何も思い煩わないで」とみことばは言います。問題や不安がありますとそれにのみ込まれて神から目を離してしまうので、ますます心がイライラし、不安が募るばかりです。だがそういう時にこそ神に目を注ぎ、問題の一つ一つを祈りをもって、神に訴え続けるなら心に平安が与えられ、冷静に対応できるようにされるのです。
聖書の神は死んだ神でなく生きて働きたもう神です。ほんとうに心から信じてより頼む者を決して無視したり、忘れたりなさいません。何らかの形で答えてくださいます。
神は人々を愛しており、特に信じる者には常に最善をなしてくださるお方です。また、神は私たちの心を満たし、喜びと平安を与えてくださいます。教会において共に神さまを讃美しませんか
カルバリー・バプテト高尾キリスト教会はプロテスタントであり、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)、エホバの証人(ものみの塔)、モルモン教(末日聖徒イエス・キリスト教会)とは一切関係はありません。
