
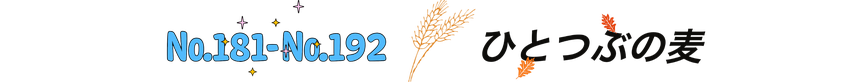
-------------------------------------
(NO.192) クリスマスーそれは救い主の誕生
「きょうダビデの町で、あなたがたのために、救い主がお生まれになりました。
この方こそ主キリストです。」 (ルカの福音書2章11節)
今年もイエス・キリストのご降誕をお祝いするクリスマスの季節になりました。クリスマスについて三つのことを考えてみましょう。
一 神が人となられたこと
イエス・キリストは神の御子です。神として永遠の昔から存在していましたが、時至って父なる神から救い主(メシヤ)として人間の姿をもってこの世に遣わされたのです。
即ち、神が人間の姿をとって現れたのです。このことについて聖書は「キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自身を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。」(ピリピ人への手紙2章6~7節前半)と記しています。
二 何時、どこにお生まれになったのか
イエス・キリストがお生まれになられた年を元年として数えられている西暦は、今年2014年ですが、計算上、4~6年の違いがあります。キリストの誕生は史実に基づいています。誕生地は、エルサレムの南8キロのベツレヘムです。ここは育ての親ヨセフの出身地で、住民登録せよとの勅令をうけて、その先祖の出身地ベツレヘムに滞在中にキリストは生まれました。
メシヤはベツレヘムに生まれることが、何世紀も前から預言者により預言されていた地です。
三 だれのためにお生まれになられたのか
冒頭の聖句にありました「あなたがたのために」です。聖書を読むすべての人のため及びこのトラクト(印刷物)をお読みになられたあなたのために、イエス・キリストは、お生まれになられたのです。私たちは無限なるまことの神を、人間となられた神の御子イエス・キリストを通してのみ正確に知り、そして信じることが出来るのです。
どうぞ高尾キリスト教会のクリスマス礼拝(12月21日)に是非おいでくださいますようお待ち申し上げます
-------------------------------------
(NO.191) 神の子ども
「この方はご自分のくにに来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。
しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子どもと
される特権をお与えになった。」 (ヨハネの福音書1章11~12節)
神は全人類の救い主としてご自身の御子を具体的にこの世にお遣わしになられるとき、先駆者として預言者を送り、メシヤ(救い主)を人々が受け入れるよう心の準備をさせました。
その預言者の名はヨハネ。メシヤを受け入れる心の準備の出来た者にバプテスマ(洗礼)を
さずけました。それ故、バプテスマのヨハネと呼ばれ、他のヨハネと区別されていました。この方がメシヤですよ、とのヨハネの証言は大変重要なことでした。メシヤであられるイエス・キリストを正確にあかしすることはどんなに強調しても、言い過ぎとはならない程、大切なことでした。最初、間違うならとり返しがつかないのです。
このことは今日も同様です。キリスト教の2千年の歴史において、イエス・キリストについて誤った説や見解を述べる人々がおりました。今日にもそれは続いています。聖書の説くイエス・キリストと異なる教えに従うなら、聖書の約束に基づく真の救いも、永遠のいのちの賦与(神が配り与えること)もなく、まして神の子ども(身分)とされる特権も与えられません。
『…ご自分の民は受け入れなかった。』イエス・キリストがユダヤにお生まれになられたとき、多くのユダヤ人は主イエスを歓迎しませんでした。しかしそういう中で、主イエスを受け入れ、信じ従う者もおりました。そのように主イエスを信じ、従う者たちは「神の子ども」としての特権と祝福を受けたのです。今日のおいても、聖書の示すイエス・キリストを信じ従う者に、当時の人々と同じように神の子としての身分と権利が与えられるのです。
「信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです。」
(ローマ人への手紙10章17節)
-------------------------------------
(NO.190) 証言者ヨハネ
「神から遣わされたヨハネという人が現れた。この人はあかしのために来た。光についてあかしするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光についてあかしするために来たのである。」 (ヨハネの福音書1章6~8節)
神は救い主(メシヤ)をこの世に遣わされるに当たり、この前ぶれ役として一人の預言者を送られました。その名はヨハネ。(この福音書の筆者ヨハネとは別人)。父は祭司で名はザカリヤ。ザカリヤ、エリザベツ夫婦には子供がありませんでした。しかし神は高齢のザカリヤ夫婦の願いを聞かれ、男の子を授けられたのです。
その子の名前ヨハネ(神はいつくしみ深いの意)も神からのものでした。
主イエス・キリストより半年前にヨハネは尊い使命を帯びて誕生したのです。7節「この人はあかしのために来た。光についてあかしするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。」主イエスが真の救い主であり、主イエス以外に、永遠の救いがないことなどをヨハネはのべ伝えたのです。
主イエスはまことの救い主として、人々の目を開いて、暗やみから光に、悲しみから喜びに、滅びから永遠の救いをもたらす唯一のお方です。
ヨハネの働きは決して容易ではありませんでした。御名が素直に聞き従ったわけではありません。しかし彼は主イエスをあかしし続けました。人々が主イエスを知り、その救いにあずかることを願い彼は黙しませんでした。多くの反対と迫害と戦いながら、その果ては殉教でした。
紀元一世紀のヨハネから今日まで、キリスト教会は主イエス・キリストがまことの、そして唯一の救い主であられることを宣べ伝え続けているのです。1人でも多くの方が、主イエスを知り、信じて滅びから永遠のいのちにあずかりますよう心から祈っております。
「主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。」
(使徒の働き16章31節)
-------------------------------------
(NO.189) ことばは神であった
「初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。この方は、初めに神とともにおられた。すべてのものは、この方によって造られた。造られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。」 (ヨハネの福音書1章1~3節)
福音書は、4つありますが、ヨハネの福音書はいちばん最後に書かれたものです(紀元1世紀末頃)。ヨハネは、イエス・キリストの12弟子の1人として主イエスの十字架刑、復活、昇天と最後まで主イエスに忠実に従い通した弟子です。彼は非常に長生きし、長期間熟慮し、1人でも多くの人が、主イエスは神の御子であり、救い主であられることを知り、信じて救いにあずかることを心から願ってこの福音書を書いたのです。
ヨハネは当時のギリシャ、ローマの世界への宣教に当たり、一般の人は、「キリスト」(救い主)と言っても分かりませんので、そこで採用された用語が「ことば」(原語でロゴス)という表現でした。言葉は人の心の思いや考えなどを表し、相手に伝え、その人の意見や願望などが理解できます。主イエスは正に、霊なるまことの神が人々に求めておられることやご意志を誤りなく正しくお伝えする最もふさわしいお方ロゴスなのです。
「初めに、ことばがあった」この「初め」は、原初(物事のいちばん初め)のことで、主イエスは人となられる前から神として存在しておられたのです。そして神の天地創造のみ業に関与し、被造物のすべての創造に神とともに労されました。キリスト教において最も重要なことは、人間となられたイエス・キリストを正確に知り、信じることです。キリスト教の長い歴史において、誤った教えを唱える教会が多くありました。今日もそうです。確実に、天国に入るためには、正しい聖書の教えに聞き従っていなければなりません。
「狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこから入って行く者が多いのです。いのちに至る門は小さく、その道は狭く、それを見いだす者はまれです。」 (マタイの福音書7章13~14節
-------------------------------------
(NO.188) 始められたことを完成される神
「あなたがたのうちに良い働きを始められた方は、キリスト・イエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は堅く信じているのです。
私があなたがたすべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなたがたはみな、私が投獄されているときも、福音を弁明し立証しているときも、私とともに恵みにあずかった人々であり、私は、そのようなあなたがたを、心に覚えているからです。」
(ピリピ人への手紙1章6~7節)
聖書は神のみことばですが、古くまた、執筆の事情等により、読んですんなり理解が出来るわけではありません。しかし、ちょっとした解説がありますと、よく分かります。
今月もピリピ人への手紙を学びたいと思います。どんなにすぐれた教えであっても、それを述べ伝える人がいなければ、その教えに触れることができません。福音の宣教師パウロは、海を渡ってヨーロッパにやって来ました。そこで産まれた、最初のキリスト教会がピリピ教会でした。
冒頭の聖書のみことばの中から二つの点について学びましょう。
(一)良い働きを始められた方
聖書によると、信仰即ち救いは、人間の側だけの働きによるのではなく、神からの働き、導きによって生まれるものである、ということです。礼拝に出席し、みことばの説教を聞き、聖書を読み続ける所に、神はみことばを通して働き、心が徐々に開かれていくのです。
そして信仰の決心へと導かれるのです。
(二)キリスト・イエスの日に完成される
「キリスト・イエスの日」主イエスは十字架での死の後、三日目によみがえり、多くの弟子たちの見ている前で挙(あ)げられました。
その主イエスがもう一度地上においでになります。そのことが「キリスト・イエスの日」なのです。その日はキリスト者の救いが完成する日であり、祝福と栄誉を受ける時なのです。
キリストを信じる信仰は、決して無駄に終わることはありません。
-------------------------------------
(NO.187) 良い知らせを広めることへの参与
「私は、あなたがたのことを思うごとに私の神に感謝し、あなたがたすべてのために祈るごとに、いつも喜びをもって祈り、あなたがたが、最初の日から今日まで、福音を広めることにあずかって来たことを感謝しています。」 (ピリピ人への手紙1章3~5節)
この聖書のことばを今月ご一緒に学びたいと思います。神のことばである聖書そのものを学ぶ機会を与えられましたことを感謝し、喜びをもって学び続けましょう。
福音(良い知らせ)は、今まで小アジアを中心に宣べ伝えられていましたが、このたび初めてヨーロッパに伝えられたのです。それがギリシャのマケドニヤ州の大都市ピリピでした。
新しい所で何かを始めるということは、どんな働きであっても多くの困難や抵抗があるものです。見てすぐわかる物品の販売等と異なり、例え「良い知らせ」であっても、聞いてすぐ理解できるものとは違いますのでなおさらです。しかし中には、パウロの語るメッセージに心が開かれ、イエスを信じる者たちも起こされるのです。聞き方が大事なんですね。それは何時の時代でも同様です。福音に熱心に耳を傾け、受けとめる時、そこに変化が生じるのです。即ち、心が変えられるのです。こうしてピリピの町にキリスト教会が生まれたのです。
その教会がどのような教会であったかを冒頭のことばが良く表しています。
「感謝」パウロは忠実な信仰者である彼らのことを思い出した時のことを述べているのです。複雑な人間関係の中で、感謝できる友人を持っていることは幸いなことです。
「喜びをもって祈れること」ここにもピリピ教会員の誠実な生き方を見ます。今日の私たちの信仰のあり方を教えられます。
「良い知らせを広めることに参加している」どんなに熱心な宣教師であっても、自分一人でその働きを発展・継続させることはできません。教会員の祈りと、物心両面による支援が必要なのです。昔も今もこのことは変わりません。キリスト教会は常に一つとなって、主イエスの福音を宣べ伝えていくのです。それが教会の使命です
-------------------------------------
(NO.186) 恵みと平安
「キリスト・イエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリスト・イエスにあるすべての聖徒たち、また監督と執事たちへ。どうか、私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にありますように。」
(ピリピ人への手紙1章1~2節)
ここの箇所はこの手紙のあいさつです。発信者はパウロとテモテの2人記されていますが、おもにパウロの執筆と思われます。宛先はピリピ教会の全クリスチャンと教会において指導の任に当たっている人々となっています。
ピリピはギリシャのマケドニヤ州の大都市でありました。交通、軍事、通商の上でも重要な町でありました。パウロがイエス・キリストの福音を携えて海を渡って来たのは、紀元50年代初め頃と思われますが、福音は初めてヨーロッパに伝えられたのです。
イエス・キリストによる永遠の救いを伝える福音がどんなに素晴らしい教えであってもそれを聞かなければ何の意味も効果もありません。そのためには、真剣に福音を伝える人がどうしても必要なのです。パウロは、初めはイエス・キリストに徹底的に反抗した人物でしたが、復活されたキリストに会いその人生は180度転換させられたのです。
人はよく相手の事や主張の真価が全く分からないのに、反対を唱えたり、運動を起こしたりします。パウロもそうでした。しかし、キリストはどういうお方なのか、何をされたのかを正確に知ったとき、彼の心の目が醒め、キリストに仕えることが自分の生きる使命であることを示されたのです。この世には知らなくても良いことと、どうしても知らなければならないことがあります。パウロはその「どうしても知らなければならないこと」(キリストによる永遠の救い)に命をかけたのです。
教会においてご一緒に聖書を学びませんか。キリストからの恵みと平安がありますように。
-------------------------------------
(NO.185) イエスのまことの家族
「さて、イエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて、人をやり、イエスを呼ばせた。
大ぜいの人がイエスを囲んですわっていたが、『ご覧なさい。あなたのお母さんと兄弟たちが、
外であなたをたずねています。』と言った。すると、イエスは彼らに答えて言われた。『わた
しの母とはだれのことですか。また、兄弟たちとはだれのことですか。』そして、自分の回り
にすわっている人たちを見回して言われた。『ご覧なさい。わたしの母、わたしの兄弟たちで
す。神のみこころを行う人はだれでも、わたしの兄弟、姉妹、また母なのです。』」
(マルコの福音書3章31~35節)
キリスト教会では、信者同士を兄弟姉妹と呼び合います。私ははじめ聞いた時、意味は分か
りませんでしたので、身内の多い教会だなぁと思いました。後に、その意味を知らされたとき、
キリスト者のことであり、キリスト者を兄弟姉妹と呼ぶほどにイエスの愛の深さに感銘を受け
ました。
イエスの母や兄弟たちが、人を介してイエスを呼んだとき、大ぜいの人がイエスを囲んで、
イエスの話(メッセージ)に真剣に耳を傾けていたのです。皆が信仰者とは限りませんが、イエ
スに救いを、また心の満たしを求めて集まっていたのです。イエスはそういう人たちを常に大
事にしておりました。「わたしの母とはだれのことですか。また、兄弟たちとはだれのことで
すか。」というイエスの言葉は、決して実の母や兄弟たちを無視したり、軽視したわけではあ
りません。ここの箇所でカギとなる言葉は、最後の「神のみこころを行う人はだれでも、わた
しの兄弟、姉妹、また母なのです。」イエスは今も、信仰者やイエスの救いを求める求道者を、
肉親のきずなに勝るとも劣らない固いきずなで結びあって、わたしの母、また兄弟姉妹と呼ん
でくださるのです。あなたもイエス・キリストの兄弟姉妹におなりになりませんか。
いつでも、日曜日の礼拝にご出席ください。お待ち申し上げます。
-------------------------------------
(NO.184) 神の前に富まない者
「ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は、心の中でこう言いながら考えた。
『どうしよう。作物をたくわえておく場所がない。』そして言った。『こうしよう。あの倉を取りこわして、もっと大きいのを建て、穀物や財産はみなそこにしまっておこう。そして、自分のたましいにこう言おう。“たましいよ。”これから先何年分もいっぱい物がためられた。さあ、安心して、食べて、飲んで、楽しめ。』しかし神は彼に言われた。
『愚か者。おまえのたましいは、今夜おまえから取り去られる。そうしたら、おまえが用意
した物は、いったいだれのものになるのか。』自分のためにたくわえても、神の前に富まない者はこのとおりです。」(ルカの福音書12章16~21節)
非常に考えさせられる話です。これはある人が、イエスに「先生、私と遺産を分けるように
私の兄弟に話してください。」と言ったことに対して、イエスは上記のようなたとえを話されたのです。この男の人には、自分のことしか眼中になかった。その現れとして、彼が強調していることは、「わたしの作物」「わたしの倉」「わたしの穀物や財産」「わたしのたましい」と「わたし」に満ち、他人には「びた一文」たりとも渡すものか、と言わんばかりの徹底した自己中心が感ぜられます。彼には貧しい人や気の毒な人々への思いやりなどはまったくありません。
さらに自分の全財産は神からの預かり物というへりくだりの心もありませんでした。
聖書はその少し前のところで、「人のいのちは財産にあるのではない」とありますように、お金や物に比例して長生きするのではありません。
自然を通して、彼の畑が豊作となったことに気づき、また「天の父は、悪い人にも良い人に
も太陽を上らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。」
(マタイの福音書5章45節)
この神の恵みに心から感謝し、神を信じ、神と人々とを愛するなら恵みによって与えられた財産は尊く、有益に用いられたことでしょう。そして彼自身、神の前に富むものとされるのです
-------------------------------------
(NO.183) キリストを知っていることのすばらしさ
「…私の主であるキリスト・イエスを知っていることのすばらしさのゆえに、いっさいのことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらをちりあくたと思っています。…」(ピリピ人への手紙3章8節)
この世には知らないでも済むことと、どうしても知らなければならない事柄があります。パウロはサウロとも呼ばれており、若くしてユダヤ教に深く進み、人間的なものにおいても頼むところがありました。彼が何に依り頼んで誇っていたのでしょうか。聖書から拾い上げてみましょう。七つあります。
1. 「八日目に割礼を受け」~律法にしたがい、正当なユダヤ教の儀式である割礼を受けた事。
2.「イスラエル民族に属し」~ヤコブを祖先とする由緒ある民族であること。
3.「ベニヤミンの分かれの者」~ヤコブの妻ラケルから生まれた末っ子で、家柄の良さを表しています。
4.「きっすいのヘブル人」~これは言葉と生活の在り方を示し、人間的なもの。
5.「律法についてはパリサイ人」~神の法律を守ることにおいて、最も厳格な派のパサイ人であること。
6.「その熱心は教会を迫害したほど」~パリサイ人としての熱心さが、ここに現れています。
イエス・キリストの教えを異端と信じ、容赦なく迫害し、それが神に対する奉仕と思っていたのです。
7.「律法による義についてならば非難されるところのない者」~自分の行いによって神のみ前に義なる者と認めていただくために、一心に律法を守ったのです。
これらの熱心さをもってキリスト者を迫害したのですが、イエス・キリストについては良く
知っていませんでした。しかし、キリスト者を捕縛しようと向かったその途上、復活された
キリストにお会いし、キリストがどういうお方なのかを知らされたのです。
キリストに対するこれまでの誤解や偏見が解消され、キリストこそ真の救い主であることを
知り、信じ、従う者とされたのです。今日も、多くの人がキリストに対する誤解や偏見を抱い
ていますが、キリストを正しく認識し、キリストによる素晴らしい救いと祝福を受けられます
ようにお祈りしています
-------------------------------------
(NO.182) 大喜びでイエスを迎えた人
「イエスは、彼(ザアカイ)に言われた。『きょう、救いがこの家に来ました。
この人もアブラハムの子なのですから。人の子(イエス)は、失われた人を捜して救うために来たのです。』」 (ルカの福音書19章9~10節)
ザアカイは取税人のかしらで金持ちでした。外国のローマ政府に納める税の徴収人で、中には決められた額以上に徴収し、自分のふところに入れる者などがおり、人々からきらわれ、罪人のように思われていました。
彼はエリコの町をお通りになるイエスを見ようとしたが、背が低く、また群衆のため見ることができませんでした。そこで前方に走り出て、そばのいちじく桑の木に登りました。ちょうどイエスはその下に来られて、上を見上げてザアカイに言われました。
「ザアカイ。急いで降りて来なさい。きょうは、あなたの家に泊まることにしてあるから。」ザアカイは、急いで降りて来て、大喜びでイエスを迎えました。これを見ていた周囲の人々は、「イエスは罪人のところに行って客となられた」とつぶやきました。
ザアカイはこれまで、イエスについていろいろ聞いて知っていました。だから「だれからでも、私がだまし取った物は、四倍にして返します」と述べています。彼は、イエスが罪深い自分の救い主である、との信仰に立っていました。
イエスは彼に言われました。「きょう、救いがこの家に来ました。…人の子(イエス)は、
失われた人(神から離れている人)を捜して救うために来たのです。」
ザアカイはイエスを自分の家に迎え入れることによって、新しい人間に変えられました。救い主イエスを心に迎え入れた罪人は、その罪を赦され、イエスと人々を愛する新しい心が与えられます。イエスは貧しい人々の救い主のみならず、富める人々の、また全人類の救い主でもあられます。
キリスト者は「信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているのです。」
(テモテへの手紙 第一 4章10節)
-------------------------------------
(NO.181) 新しく造られた者
「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。」(コリント人への手紙第二 5章17節)
新しい年を迎えました。ここ何年かは、年末年始を元旦礼拝のメッセージの準備で過ごしま
した。今年もそうでした。神は恵みの年、新しい年を増し加えてくださいました。ほんとうに
感謝です。そして今年こそ神さまや人々に迷惑や心配をかけないもっと充実した年にしたいと
心から願い、祈りをささげました。
冒頭の聖書の言葉は、新年にふさわしいと思います。
「キリストのうちにあるなら」
これはキリストを自分の救い主と信じ、拠り頼む ことです。ただキリストを信じるだけでな
く、キリストのご意志に従って生き、キリストと共に生活することです。信仰と生活がばらば
らでなく、一つとした生き方です。
「新しく造られた者」
聖書は、キリストから離れている魂は死んでおり、自ら行動を起こして、キリストを見つけ、
信じるという働きはできないことを記しております。死んだ魂は、外部からの働きがあって始
めて開かれるのです。そのために教会の礼拝や集会に出席し、聖書のおことばを聞き続けるの
です。そこに神の霊が働いて少しずつ心が開かれていくのです。人間が勝手に信じたり、拒ん
だりするのではありません。ここで必要なことは、まじめな求道心です。
「その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って…すべてが新しくなりました。」
「新しく造られる」ことは全く神のみわざです。「新生とか再生」とも言います。
神の国(天国)に入るためには、新しい人にされなければなりません。
「求めなさい。そうすれば与えられます。」(マタイの福音書7章7節)
カルバリー・バプテト高尾キリスト教会はプロテスタントであり、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)、エホバの証人(ものみの塔)、モルモン教(末日聖徒イエス・キリスト教会)とは一切関係はありません。
